※本記事にはプロモーションが含まれています。
【完全ガイド】猫のワクチン接種スケジュールと種類・費用・注意点

愛猫の健康を守るために欠かせない「ワクチン接種」。病気の予防はもちろん、万が一感染してしまった場合でも症状を軽くする効果が期待できます。しかし、「どの種類をいつ接種すればいいの?」「毎年必要?」といった疑問を持つ飼い主さんは多いものです。
この記事では、猫のワクチン接種スケジュールを完全ガイドとして、接種時期、種類、費用目安、注意点をわかりやすく解説します。

1. 猫のワクチン接種が必要な理由

猫は完全室内飼いであっても、ウイルスや細菌に感染する可能性があります。人間の衣服や靴、窓から入る虫などが病原体を運んでくることもあります。特に子猫や高齢猫は免疫力が弱いため、感染すると重症化しやすいです。
ワクチン接種を行うことで、以下のようなメリットがあります。
- 感染症の発症予防
- 感染した場合の症状軽減
- 集団感染の防止(多頭飼いの場合)
2. 猫ワクチンの種類

猫のワクチンには大きく分けて「コアワクチン」と「ノンコアワクチン」の2種類があります。コアワクチンはすべての猫に推奨される基本的な予防接種であり、ノンコアワクチンは猫の生活環境や外出の有無、他の猫との接触頻度などによって接種を検討するものです。正しい種類とタイミングで接種することが、病気の予防と健康維持に直結します。
2-1. コアワクチン(必須)

230511084233309
コアワクチンとは、生活環境に関係なくすべての猫が接種すべき基本ワクチンです。これらが予防する病気は感染力が非常に強く、かつ重症化しやすいため、未接種の場合は命に関わる危険があります。特に子猫や高齢猫、免疫力の低い猫では症状が急速に進行することが多く、予防は必須です。
代表的なコアワクチン対象の病気は以下の3つです。
- 猫ウイルス性鼻気管炎(FVR)
猫ヘルペスウイルス1型が原因で、くしゃみ、鼻水、発熱、結膜炎などの呼吸器症状を引き起こします。一度感染するとウイルスが神経節に潜伏し、ストレスや免疫低下時に再発することがあります。慢性的な鼻炎や目の炎症に悩まされる猫も多いため、予防は非常に重要です。 - 猫カリシウイルス感染症(FCV)
呼吸器症状だけでなく、口内炎や舌潰瘍など口腔内の痛みを伴う症状が特徴です。重症例では肺炎や関節炎を併発し、食欲不振や歩行困難を引き起こすこともあります。感染力が強く、集団飼育環境では短期間で広がります。 - 猫汎白血球減少症(FPV)
猫パルボウイルスが原因で、激しい嘔吐や下痢、急激な脱水、白血球の著しい減少を引き起こします。致死率が非常に高く、特に生後間もない子猫では数日以内に死亡する危険があります。ウイルスは環境中で長期間生存できるため、屋内飼いでも感染の可能性があります。
これら3つの病気を一度に予防できるのが「3種混合ワクチン」です。1回の接種で広範囲の感染症から猫を守れるため、動物病院で最も広く使用されています。初年度は複数回の接種、その後は年1回程度のブースター接種を行うのが一般的です。
2-2. ノンコアワクチン(生活環境に応じて)

ノンコアワクチンは、猫の生活環境や行動範囲によって接種を検討するワクチンです。外に出る機会がある猫、他の猫と接触する機会がある猫、保護施設や猫カフェなど多頭環境に出入りする猫は、これらのワクチンを接種することで感染リスクを大きく減らせます。
- 猫白血病ウイルス感染症(FeLV)
猫白血病ウイルスは、唾液や血液を介して感染します。感染すると免疫力の低下、貧血、腫瘍の発生など重篤な症状を引き起こし、慢性経過で命を縮めることもあります。完全室内飼いで他の猫と接触がない場合はリスクが低いですが、外出や猫同士の接触がある場合は接種が推奨されます。 - 猫クラミジア感染症(Chlamydia felis)
主に結膜炎や鼻炎を引き起こし、くしゃみや目やにが長引くことが特徴です。多頭飼育環境では特に感染しやすく、猫同士の接触や飛沫によって広がります。軽症でも慢性的に症状が続くことがあるため、感染リスクが高い場合は接種を検討しましょう。 - 狂犬病
猫にも感染する致死率ほぼ100%の病気で、発症後の有効な治療法はありません。日本では猫の狂犬病ワクチン接種は義務ではありませんが、海外渡航や狂犬病発生地域への移動時には接種が求められることがあります。万が一の人への感染を防ぐ意味でも重要です。
ノンコアワクチンは、すべての猫に必須ではありませんが、生活環境や行動パターンによっては感染リスクが高まるため、獣医師と相談して最適な接種プランを立てることが大切です。
3. ワクチン接種スケジュール

MNS G23 N5 O0.00 Y0.50 C3.00 YT1 CT1 S250 FM0 FC000000000
3-1. 子猫の場合
子猫は生まれてすぐ、母猫の初乳から移行抗体という免疫成分を受け取ります。この移行抗体は生後2〜3か月頃まで子猫を病気から守りますが、徐々に減少していきます。抗体が減少すると病気への抵抗力が弱まるため、この時期からワクチン接種を開始することが重要です。あまり早く接種しても移行抗体の影響で免疫がつきにくく、逆に遅すぎると感染のリスクが高まります。適切なタイミングで接種を始めることが、健康な成長の第一歩となります。
| 時期 | 接種内容 | ポイント・注意点 |
|---|---|---|
| 生後8週 | 3種混合ワクチン(1回目) | 初めてのワクチン。軽い副反応(発熱・元気消失)が出ることがあるため、接種後は安静に過ごさせる。健康状態が万全な日に行うことが大切。 |
| 生後12週 | 3種混合ワクチン(2回目) | 1回目で得た免疫を強化するための接種。外出や他の猫との接触がある場合、この時期までに必ず接種を完了しておく。 |
| 生後16週 | 必要に応じて3種混合ワクチン(3回目) | 移行抗体の影響が長く残る子猫では、免疫定着を確実にするため3回目を接種。特に感染症リスクの高い地域や環境では推奨される。 |
| 1歳 | 追加接種(ブースター) | 子猫期に形成された免疫を長期間維持するために行う。1歳の接種は、その後の免疫力を安定させる重要な節目となる。 |
なお、子猫の体調や体重、既往歴によってはスケジュールが変更されることもあります。必ず獣医師と相談し、最適なプランを決めましょう。
3-2. 成猫の場合

過去にワクチン接種歴がない成猫や、長期間接種していない猫の場合、免疫が十分に形成されていない可能性があります。この場合は、初回接種とその3〜4週間後の2回目接種が必要です。これは子猫と同様に、1回目で免疫反応を起こし、2回目で抗体価を高めて安定させるためです。
外に出る猫や、他の猫と接触する機会がある猫は、感染症リスクが高いため特に接種が重要です。また、完全室内飼いであっても、人間や物品を介したウイルス持ち込みのリスクがあるため、予防は欠かせません。
3-3. 毎年の接種
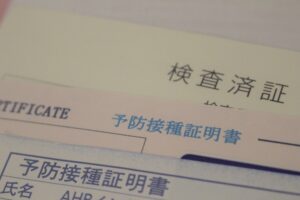
多くの動物病院では、年1回の追加接種(ブースター)を推奨しています。これは、時間の経過とともに免疫力が低下するため、定期的に刺激を与えて抗体を維持する目的があります。特に外出する猫や多頭飼育環境の猫では、年1回の接種が安心です。
近年は、ワクチンによる過剰接種を避けるために抗体検査を行い、免疫が十分であれば接種間隔を2〜3年に延ばす方法も注目されています。ただし、この方法は環境や感染リスクを考慮して慎重に判断する必要があります。抗体が低下している状態で接種を怠ると、予防できるはずの病気にかかってしまう可能性があります。
どの方法を選ぶにしても、愛猫のライフスタイルや健康状態を把握した上で、かかりつけの獣医師と相談しながら接種スケジュールを決めることが最も大切です。
4. 費用の目安

猫のワクチン接種費用は、ワクチンの種類や接種回数、動物病院の方針、地域の物価によって異なります。以下は一般的な目安です。
- 3種混合ワクチン:3,000〜6,000円
猫ウイルス性鼻気管炎、猫カリシウイルス感染症、猫汎白血球減少症を予防する基本的なワクチンです。完全室内飼いの猫でも推奨されることが多く、最も一般的に接種されます。 - 5種混合ワクチン:5,000〜8,000円
3種混合に加えて、猫白血病ウイルス感染症や猫クラミジア感染症を予防できるタイプです。外出や他の猫との接触がある場合や、多頭飼育環境では選ばれることが多いです。 - 猫白血病ワクチン(単独):3,000〜5,000円
猫白血病ウイルス感染症を単独で予防するワクチンです。すでに3種混合ワクチンを接種している猫に追加で行う場合や、感染リスクの高い猫に用いられます。
これらの金額はあくまで目安であり、動物病院や地域によって価格は変動します。都市部ではやや高く、地方では比較的安価な傾向があります。また、初診時や久しぶりの来院時には初診料(1,000〜2,000円程度)や診察料が別途かかることがあります。
さらに、ワクチン接種前には健康チェックや体温測定、場合によっては血液検査が行われることもあり、その分の費用が加算されます。特に初めてのワクチン接種や高齢猫の場合、体調確認のための事前検査が推奨されます。
費用を抑える方法としては、地域の動物愛護センターや自治体が実施する予防接種キャンペーンを利用する、複数頭同時に接種して割引を受けるなどがあります。ただし、価格だけで選ぶのではなく、接種前後のケアや病院の信頼性も重視しましょう。
5. ワクチン接種前後の注意点

接種前の注意点
- 体調が良い日に接種する
ワクチンは免疫システムを刺激して抗体を作らせるため、猫が健康な状態でないと十分な効果が得られません。発熱、下痢、嘔吐、食欲不振などの症状がある場合は接種を延期し、体調が回復してから行いましょう。特に子猫や高齢猫は体調の変化に敏感なため、当日の診察で獣医師にしっかり確認してもらうことが大切です。 - 寄生虫予防や駆虫が済んでいること
ノミ、ダニ、回虫などの寄生虫がいると、免疫力が低下してワクチン効果が下がる可能性があります。接種の1〜2週間前には駆虫や寄生虫予防を済ませておくのが望ましいです。 - 空腹・満腹すぎる状態は避ける
接種当日は、普段通りの食事を与えましょう。空腹すぎるとストレスがかかり、満腹すぎると移動や注射のストレスで吐き戻す可能性があります。 - ストレスを最小限にする準備
キャリーケースに慣らしておく、病院までの移動時間を短くする、好きなおもちゃやタオルを持参するなど、猫の緊張を和らげる工夫も効果的です。
接種後の注意点
- 当日は安静に過ごさせる
ワクチン接種後は免疫反応で軽いだるさや発熱が出ることがあります。激しく遊ばせたり、長時間の移動は避け、自宅で静かに休ませましょう。 - 激しい運動やシャンプーは避ける(2〜3日)
運動や入浴は体力を消耗し、免疫形成の妨げになることがあります。特にシャンプーは体温低下やストレスを招くため、接種後2〜3日は控えましょう。 - 注射部位の腫れや発熱、元気消失などの異常を観察
接種後は注射した部分が少し腫れることがありますが、数日で自然に治まります。ただし、腫れが大きくなる、痛みが強い、発熱や呼吸困難などの異常が出た場合は、すぐに動物病院へ連絡してください。 - 重度のアレルギー反応に注意
ごくまれに、接種後30分以内に顔やまぶたの腫れ、嘔吐、呼吸困難などのアレルギー症状(アナフィラキシー)が出ることがあります。接種後はできるだけ病院近くで様子を見てから帰宅すると安心です。
接種前後の適切な管理は、ワクチンの効果を最大限に発揮させるだけでなく、副作用や体調不良のリスクを減らすことにもつながります。日常の健康観察を欠かさず、気になる変化があれば早めに獣医師へ相談しましょう。
6. よくある質問(FAQ)

Q1. 完全室内飼いでもワクチン接種は必要ですか?
はい、必要です。完全室内飼いであっても、人間や物を介して病原体が家の中に持ち込まれる可能性があります。例えば、飼い主が外出先で他の動物と接触したり、靴や服に付着したウイルスが室内に入り込んだりすることがあります。また、網戸や窓から入ってくる虫が感染源になるケースもゼロではありません。さらに、災害や引っ越し、通院などで突然外に出ざるを得ない状況が発生することも考えられます。これらのリスクを考えると、室内飼いの猫でもワクチン接種を行うことが安全です。
Q2. 副作用はありますか?
ワクチン接種後、軽い副作用として一時的な発熱、食欲不振、倦怠感が出ることがあります。これらは免疫反応の一部で、通常は1〜2日程度で自然に回復します。注射部位が少し腫れたり、触ると痛がることもありますが、多くの場合は数日以内に治まります。
ごくまれに重度のアレルギー反応(アナフィラキシー)が起こることがあります。症状には顔やまぶたの腫れ、呼吸困難、嘔吐、ぐったりするなどがあり、放置すると命に関わる場合があります。このため、接種後30分程度は動物病院で待機して様子を見るか、少なくともすぐに連絡できる距離で経過観察をすることが推奨されます。
Q3. 接種間隔を延ばしても大丈夫ですか?
猫によっては、抗体検査を行って十分な免疫が確認できれば、接種間隔を延ばすことが可能です。近年は過剰接種を避けるため、抗体価測定による接種計画が注目されています。ただし、この方法は猫の生活環境や健康状態、感染症の流行状況を考慮して慎重に判断する必要があります。
外出する猫、多頭飼育環境の猫、保護施設や猫カフェなど不特定多数の猫と接触する可能性がある猫は、感染リスクが高いため年1回の接種が安全策とされています。逆に完全室内飼いで他の猫との接触がない場合は、抗体検査で十分な数値が出ていれば2〜3年ごとの接種でも良いケースがありますが、必ず獣医師と相談して最適な間隔を決めましょう。
まとめ

猫のワクチン接種は、愛猫を命に関わる重大な感染症から守るための非常に重要な習慣です。特に、猫ウイルス性鼻気管炎や猫カリシウイルス感染症、猫汎白血球減少症などは、発症すると重症化しやすく、治療が困難な場合もあります。ワクチン接種によってこれらの病気を予防することは、愛猫の健康寿命を延ばすうえで欠かせない対策です。
子猫期は母猫からの移行抗体が減少する生後2〜3か月頃から接種を始め、スケジュール通りに2回または3回の初期接種を行うことが推奨されます。成猫になってからも、過去に接種歴がない場合は初回と3〜4週間後の2回接種、その後は年1回の追加接種が基本です。近年では抗体検査を活用して接種間隔を調整する方法もありますが、生活環境や感染リスクによって最適な頻度は異なります。
ワクチンの種類や費用は動物病院や地域によって異なります。一般的な3種混合ワクチンから、猫白血病ウイルスやクラミジア感染症にも対応する多種混合ワクチンまで、猫の生活環境や外出頻度に応じた選択が必要です。かかりつけ医と相談しながら、愛猫にとって最も安全で効果的なプランを立てましょう。
また、接種前後の体調管理や副作用への注意も大切です。体調が万全な日に接種し、接種後は安静に過ごさせ、異常があればすぐに病院へ連絡するよう心がけましょう。こうした細やかな配慮が、ワクチンの効果を最大限に引き出します。
健康で元気な日々を長く一緒に過ごすためには、ワクチン接種を単なる「義務」ではなく「愛情の一環」として捉えることが大切です。計画的な接種と日々の健康チェックで、愛猫の笑顔と安心を守り続けましょう。



コメント